筆者の友人の編著書の帯紙に「ほんの少しの微生物知識が、食中毒事故から企業を救う!」と書かれていて、強い説得力がある。(社)日本乳容器・機器協会の会員も微生物とは縁が深い。包装は微生物汚染を遮断する基本対策であり、洗浄・殺菌装置は食品産業の安全の要である。また包装する内容物として、殺菌製品だけでなく、発酵食品も扱われる。本稿では、微生物の一般的知識、有害微生物への対策、有用微生物の利用について3回に分けて概説する。
森地 敏樹
1.微生物についての一般的知識
微生物とは? 「微生物」とは顕微鏡の助けを借りなければ肉眼では見えない微小な生物の総称で、細菌、酵母、かび(糸状菌)、微細藻類、原虫などはすべて微生物に属する。ウイルスは厳密にいうと生物ではないが、便宜的に微生物の仲間として取り扱われる。
微生物の代表ともいうべき「細菌(バクテリア)」は、約35億年前に出現した地球上で最古の生物である。細菌は、硬い細胞壁をもつ単細胞の微生物で、通常は1個の細胞が2個に分裂する二分裂法で増殖する。その大きさは0.5~10μm程度である。細菌の遺伝を支配するDNAは、裸のままで核様体として細胞内に存在する。このような原始的な体制を残した生物は原核生物と呼ばれ、核膜に包まれた細胞核にDNA染色体が収められている動物、植物、菌類、藻類、原虫などの真核生物と区別される。かび・酵母は真菌と総称され、真核生物に分類される微生物である。
微生物の種類と分布 現存生物の種(生物分類の基本単位)の数は約290万種と言われている。このうち、哺乳類で記載されている種の数は約4,500種、細菌類の既知の種の数もほぼ同数の4,800種、真菌類では47,000種と報告されている。ただし、地球上の哺乳類については事実上100%が既に命名されているが、細菌で記載された種は推定総菌種数の5~10%程度、研究者によっては1%以下と考えられており、まだ分離されていない未知の細菌が圧倒的に多数を占めることは間違いない。真菌類の場合も同様である。
微生物は土壌、水中、空中、生物圏などにあまねく分布している。例えば、1gの庭土の中には100万から1億個の微生物が生息し、ヒトや動物の腸管内容物には1g当り100億ないし1000億個に及ぶ微生物が存在する。しかも微生物の中には100℃に近い高温、極度に乾燥した砂漠、極寒の地域、さらに強酸性、あるいは栄養成分がほとんど含まれていない極限環境にも生息するものがあって、その生命力は強靭である。
人類と微生物との関係 人類との関係について言えば、微生物はしばしば「黴(ばい)菌」と呼ばれ、ヒト・家畜・作物などの病気を引き起こし、また物を腐らせるため、人々に嫌われることが多い。しかし一方で、微生物は私たちの身近に共存して重要な役割を果たしており、人類は昔からそれと知らずに微生物を巧みに利用してきた側面もある。
食べ物の腐敗は微生物によって起こる不都合な変化の一つであることは間違いないが、すこし視点を変えれば微生物は地球上の物質循環において“掃除屋”として様々な物質の最終分解を担当しているということができる。もしもこのような浄化作業を担う微生物が存在しなければ、地球上はいかに悲惨な状態に陥るか、想像するだけでもおぞましい話である。地球上の窒素循環の概要を図1に示した。生物圏と大気の間で、窒素ガス→アンモニア→硝酸→窒素ガスという大きな循環があり、いずれの過程も微生物によって担われている。また、生物圏の有機態窒素を無機態に戻す役割も微生物が果たしていることが分かる。
木材家屋の害虫であるシロアリは枯死した植物を独占して繁栄しているが、さらにシロアリを食べる昆虫や小動物がたくさんいて、これらの捕食者の重要なタンパク源となっている。植物の遺体から始まるこの腐食連鎖の第一段階であるシロアリの消化管にはたくさんの微生物(主として原虫と細菌)が生息していて、これらがセルロースを分解して酢酸を生成しシロアリのエネルギー源として利用される(ただし、シロアリ自身もセルラーゼを有するという説もある)。同じような共生関係は、ウシ、ヤギ、ヒツジなどの草食動物にも見られる。これらの反芻動物はルーメンと呼ばれる第1胃が発達しており、そこには多くの種類の細菌、原虫、菌類が大量に存在し、これらの微生物の働きによってヒトが利用できない牧草類を栄養源として、私たちに乳、肉、毛皮などを提供してくれる。
病原細菌と乳酸菌発見の歴史 人類が微生物の姿を初めて見たのは17世紀後半になってからである。オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックは1674年に自作の顕微鏡で微生物を発見し、微小動物と名付けて記録した。その後、細菌が純粋に分離されるまで約200年が経過し、1876年にドイツのロベルト・コッホがゼラチンで固めた固形培地を用いて、炭疽に罹った動物から炭疽菌を分離した。この発見以後、1897年までの約20年間に結核菌、コレラ菌、破傷風菌、ペスト菌、赤痢菌などの病原細菌が次々と発見された。
一方、「乳酸を生成する細菌」は微生物学の祖と仰がれるルイ・パスツールによって1857年に発見されたが、英国のJ. リスターが酸乳を何回も繰り返して希釈し、1滴に1個の菌が含まれるように工夫して、実際に乳酸菌(現行の分類ではラクトコックス・ラクチス)を単離したのは1878年である。その後、平板培養法により、1900年にE. モローが人工栄養児のふん便からアシドフィルス菌を分離し、1904年にE. メチニコフがヨーグルトの特徴的な乳酸菌を発見した。また、ビフィズス菌は1899年にフランスのH. ティシエによって健康な母乳栄養児のふん便から初めて分離された。
細菌における菌種、菌株の意義 「乳酸菌」とは炭水化物(糖類など)を発酵してエネルギーを獲得し、多量の乳酸を生成する一群の細菌の総称である。細胞形態から球菌と桿菌に大別される。一方、ヒトに及ぼす健康効果でしばしば話題となるビフィズス菌は、その主要生産物が乳酸と酢酸であり、酸素存在下で生育できない偏性嫌気性菌で、通常の乳酸菌とは異なる種類の細菌である。
細菌の体系的分類においては、動物や植物と同様に二名法が適用される。すなわち、ラテン語の名詞の属名と種の特徴を示す形容詞句の2語を組み合わせて種を表現する世界共通の学名である。例えば、大腸菌の学名はエシェリッヒア・コリで、属名は発見者(エシェリッヒ)の名、コリは大腸の意味である。乳酸菌には現在30を超える属が報告され、250以上の種が正式に記載されている。ビフィズス菌は乳酸桿菌として扱われたこともあったが、1965年にビフィドバクテリウム属として独立した。現在までに32菌種9亜種が登録されており、ティシエが発見したのはビフィドバクテリウム・ビフィダムである。
上記の学名(種)は、私たちの使う姓名に相当する。しかし世の中には同姓同名の人も存在し、当然個人差がある。風味の優れた発酵乳をつくる、あるいは有益な健康効果を求める場合などは、その目的に適う菌種に属する特定の「菌株」を使用する。菌株は唯一無二のものであり、実用面では菌株が最も重視される。菌株は、種名のあとに保管機関と番号、記号、分離者の名前などを付けて明示する。
参考書 ① 小久保彌太郎編:現場で役立つ食品微生物Q&A(第3版)、241頁、中央法規出版(2011)、② 日本農芸化学会編:人に役立つ微生物のはなし、227頁、学会出版センター(2002)
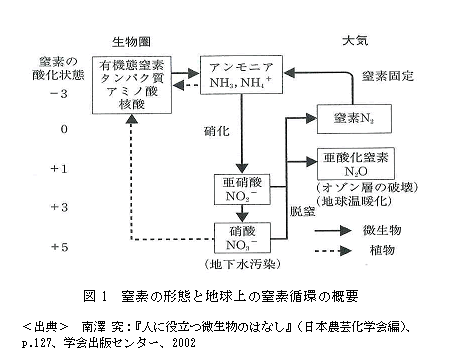
2.有害微生物とその対策
病原微生物 生物の病気が起こる原因となる病原微生物(ウイルス、細菌、真菌、原虫など)にはいろいろな種類がある。ヒトの感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、感染力および罹患した場合の重篤性などに基づき、一類~五類に分類される。一類感染症はエボラ出血熱、痘そう(天然痘)、ペストなど7疾病、二類感染症は急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1)など5疾病、三類感染症にはコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスが指定されており、これらの病原菌5菌種(いずれも細菌)については、飲食が原因で発生した場合は食中毒原因物質として扱われる。
食中毒原因菌 最近の食中毒の発生状況と主な原因物質を表1に示した。平成13年から22年までのわが国の食中毒の事件数は年間約千~二千件、患者数は二万~四万の範囲にあり、過去10年間の平均値は事件数1,500、患者数28,000名となっている。ただし、実際の発生件数や患者数は統計よりはるかに多いと推定される。2010年の食中毒によるサルモネラ症とカンピロバクター感染症の患者数を日本と米国で比べると、米国の数値は20~22倍高くなっており、日米の人口差(米国が約2.4倍)を考慮しても10倍近い開きがある。なお、わが国と世界各国の食中毒の詳細情報を知るには、特定非営利活動法人 食の安全を確保するための微生物検査協議会が提供する「世界における食中毒情報」(第9版、2011)が便利である。
表1の通り、21世紀に入ってから10年間のわが国の食中毒の原因物質として、細菌が事件数では66%(範囲50~80%)、患者数では49%(25~67%)を占めた。原因菌の種類は、事件数ではカンピロバクター、患者数ではサルモネラ属菌が1位となっている。平成13年から10年間の死者数は腸管出血性大腸菌とサルモネラ属菌感染でそれぞれ10名、6名であった。ウェルシュ菌は嫌気性芽胞形成菌で耐熱性が高く、患者数も多い。黄色ブドウ球菌は食品中で耐熱性毒素(エンテロトキシン)を産生し、典型的な毒素型食中毒を起こす。
ウイルスも食中毒の原因物質として重要であり、過去10年間を見ると事件数では24%(範囲15~35%)、患者数では48%(31~73%)を占めた。種類としてはノロウイルスが圧倒的多数である。ノロウイルスはヒトの腸管でしか増殖できず、ごく少数個(10~100個)でも発病する。冬季の事件例が多く、ヒト→ヒトの二次感染も重視されている。
食中毒予防3原則 主に細菌性食中毒を対象に考案された、①汚染防止、②増殖防止、③殺菌の3原則をいう。これらは、①清潔、②適正な温度・時間管理、③加熱・消毒と言い換えることもできる。原則①と③はウイルス性食中毒に対しても適用される。FAO/WHO国際食品規格委員会は、国際基準のガイドライン「食品衛生の一般原則」を示した。この内容をわが国では「一般的衛生管理プログラム」と呼ぶが、まずこの原則を満たすことにより原材料と作業環境からの汚染防止を確実に行い、次いで食品の取扱いに直接関係する重要事項にHACCPシステムを導入して、食品中に存在する可能性のある病原微生物の増殖防止と殺菌を確実に実施する。ISO22000:食品安全マネジメントシステム(2005)は食品衛生の一般原則を前提条件プログラムとし、それとHACCPプランを組み合わせたもので、ISOマネジメントシステムがもつ経営的手法をミックスしている点に特徴がある。
腐敗を起こす微生物 食品の腐敗に関与する微生物の種類は非常に多い。食品の原材料や土壌、水圏、空中などに広く分布する細菌や真菌類である。細菌は生育適温によって、高温細菌、中温細菌、低温細菌に大別される。高温細菌は55℃以上で増殖できる細菌群で、最適温度は55~70℃付近にあり、30℃以下では増殖しない。耐熱性の高い芽胞を形成し、レトルト食品などの高温での腐敗で問題となる。中温細菌の最適温度は25~40℃付近にあり、一般に5℃以下あるいは50℃以上では増殖できない。多くの腐敗細菌はこの菌群に属する。低温細菌は生育の適温に関係なく、7℃またはそれ以下の低温で増殖可能な菌群で、冷蔵を要する食品の低温での腐敗の原因となる。なお、ごく少数ではあるが、低温性病原細菌(リステリア・モノサイトゲネスなど)も存在するので、生の動物性食品の長期にわたる冷蔵の際に注意を要する。
食品の微生物制御に適用される原理と方法 食品の微生物制御に適用される原理は、①遮断(汚染防止)、②除菌、③抑制(静菌)、④殺菌に大別できる。「遮断」の方法は包装、コーティング、クリーンルームなど、「除菌」の方法は洗浄、遠心分離、限外濾過、電気的除菌など、「静菌」の方法は低温保持(冷蔵、冷凍)、水分活性低下(濃縮、乾燥)、気相調節(真空、脱酸素剤、ガス置換)、化学物質添加(食塩、糖、有機酸、アルカリ、天然抗菌物質、食品添加物)など、「殺菌」の方法としては各種熱殺菌、冷殺菌(殺菌剤、ガス殺菌、オゾン、γ線、紫外線)、超高圧、電気的衝撃などである。缶詰やレトルトパウチ食品などの加熱殺菌は商業的無菌性の確保を目指すもので、微生物すべてを殺滅する「滅菌」とは区別される。
静菌効果を有する物質 保存性の低い食品に比較的短期間の腐敗・変敗を抑える目的で使用する物質を日持向上剤と呼び、保存料とは区別して用いられる(物質名で表示)。静菌効果をもつ有機酸類、グリシン、リゾチーム、グリセリン中鎖脂肪酸エステル、香辛料抽出物などが使用される。グリシンは細菌の細胞壁合成を阻害し、特に耐熱性芽胞形成菌に有効である。
一方、「人々が長年にわたり食品として、あるいは食品とともに、何らの害作用もなしに食べてきた植物、動物あるいは微生物起源の抗菌性物質」はバイオプリザバティブ(biopreservative)と呼ばれる。この定義に当てはまる物質の多くは、日持向上剤として利用されている。乳酸菌は代表的なバイオプリザバティブであり、ラクトコックス・ラクチスが産生するナイシン(アミノ酸残基34個のペプチド)はグラム陽性細菌全般に抗菌活性を示し、特に芽胞に対する阻害作用は有用と考えられる。ナイシンは平成21年に食品添加物(保存料、製造用剤)として認可された。
わが国における牛乳の加熱殺菌法の変遷 国際的に見ると、牛乳の低温保持殺菌法(パスツリゼーション)は19世紀末に企業化されたが、本法に用いる保持殺菌機が日本に導入されたのは大正末期から昭和初期頃である。昭和8年の牛乳営業取締規則(内務省令)において初めて牛乳の殺菌方法が制定され、低温殺菌(63~65℃・30分)または高温殺菌(95℃以上・20分)が義務づけられた。食品衛生法の施行に伴い、昭和26年に公布された乳等省令では、牛乳の殺菌方法として、62~65℃・30分加熱あるいは75℃以上・15分加熱と改められた。従来はウシ型結核菌が殺菌指標菌であったが、その後62℃・30分加熱ではQ熱病原体が生き残る可能性が指摘され、平成14年に、現行の通り、保持式により63℃・30分加熱、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する加熱方法と定められた。HTST法は昭和27年、UHT法は昭和32年に導入された。また、平成14年には65℃以上・30分以上の連続殺菌法が認められた。なお、飲用乳の常温保存可能品が認可されたのは昭和60年である。
食品衛生微生物検査法の動向 微生物検査は、病院での臨床検査、行政検査機関による収去検査と食中毒発生時の緊急検査、登録検査機関における食品微生物検査ならびに食品製造工場における自主管理検査に大別される。現在、食品微生物検査の簡易化、迅速化に関する進歩は著しい。例えば、大腸菌・大腸菌群などの検査用に合成酵素基質培地が各種市販され、特異的で迅速な免疫検査法やPCR法なども盛んに利用されている。また、検査法の国際化傾向も注目される。一例を挙げると、平成23年に生食用食肉(牛肉)の規格基準が設定された。対象微生物は腸管出血性大腸菌とサルモネラ属菌で、腸内細菌科菌群(Enterobacteriaceae)を指標菌とするが、その検出にはISO試験法が採用された。なお、加工食品等に分布する微生物は食品に加えられる各種処理によって半致死的な損傷を受けており、培養条件が不適切だと死滅しやすい。このような食品微生物検査上の問題点についても最近研究が進んできている。
参考書 ① 仲西寿男・丸山務 監修:食品由来感染症と食品微生物、616頁、中央法規出版(2009)、② 清水潮:食中毒のリスクと人間社会、225頁、幸書房(2008)、③ 森地敏樹 監修:食品微生物検査マニュアル《改訂第2版》、323頁、栄研化学株式会社(2009)、④ 伊藤武・森地敏樹 編著:食品のストレス環境と微生物―その挙動・制御と検出―、323頁、サイエンスフォーラム(2004)
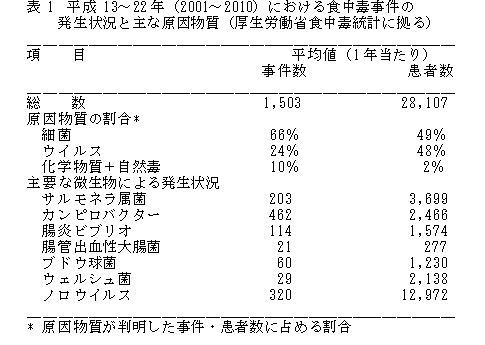
3.有用微生物とその利用
人に役立つ微生物の働きは、発酵食品の製造や有用物質の生産のみならず、環境の浄化、動植物との共生、病害虫の防除、バイオマス資源からのエネルギー生産など極めて多岐にわたるが、ここでは、有用物質の生産ならびに発酵食品とそれに関わる乳酸菌の働きを中心に述べる。
微生物による有用物質の生産 私たちは微生物を利用して様な有用物質を生産している。大別すると、アルコール、有機酸、炭水化物、ビタミン、アミノ酸、核酸関連物質、酵素・タンパク質などのほか、二次代謝産物(抗生物質など)、組換えタンパク質(ヒト成長ホルモン、インスリンなど)、低分子生理活性物質などに分けられる。本稿では抗生物質とアミノ酸生産を取り上げる。
抗生物質 微生物がつくる有用物質として、感染症から人類の多くの命を救った抗生物質が先ず注目される。1928年に英国のフレミングは青カビがブドウ球菌の生育を阻止する物質をつくることを発見し、ペニシリンと命名したが、単離はできなかった。その後、1940年にオクスフォード大学のフローリーらがペニシリンの抽出に成功し、その優れた治療効果を証明した。この「ペニシリンの再発見」とペニシリンGの実用化により、感染症の臨床治療は一変し、第二次世界大戦中、何万もの兵士や市民の命が救われた。人類に対しこのような貢献をする物質を営利の対象とすべきでないと考えて、英国の科学者たちはペニシリンの特許を出願しなかった。第二次大戦中、わが国でも「碧素研究会」が発足し、1946年に日本ペニシリン協会が設立された。当時、連合軍司令部の指導による産学官の協力体制のもと、わが国のペニシリン製造のための取組みが開始された。米国の著名なペニシリン研究者フォスター教授が来日し、米国が英国と協力して6年間に巨額の費用をかけて蓄積したペニシリン製造のノウハウを3日間で詳細に公開し、菌株を分譲し、工場を視察・指導した。敗戦の虚脱状態のなか、このペニシリン生産の工業化は日本復興の力強い原動力となった(庄村喬、参考書①、p.368)。
糸状菌がつくるペニシリンに続いて、ストレプトマイシン(結核菌に著効)、カナマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、アクチノマイシンなど、放線菌が生産する多くの抗生物質が実用化された。なお、ペニシリンは細菌の細胞壁合成を阻害し、細胞壁を持たないヒトへの毒性が極めて低い“理想的な”抗生物質といえる。その後、セファロスポリウム(カビに属する不完全菌)が生産するセファロスポリンが単離されたが、これもペニシリンと同様なβ‐ラクタム系抗生物質で、広く用いられている。また、現在はウイルスや真菌等の感染症に対する抗生物質も開発されている。
微生物によるアミノ酸生産 わが国の伝統的な醸造技術を土台にして、上述の抗生物質生産技術は、日本のお家芸ともいうべき微生物工業の発展を促した。旨味調味料として需要の多いグルタミン酸は、かつては小麦または大豆タンパク質の塩酸加水分解により製造され、高価であった。1956年にグルタミン酸を培地中に蓄積する細菌(コリネバクテリウム)が発見され、日本で最初にグルタミン酸発酵の工業化が成功した。これは、代謝中間産物の発酵生産という点で画期的なものであった。化学合成従属栄養細菌(エネルギーも炭素も有機化合物から獲得する細菌)は自らの生体成分であるアミノ酸を合成する能力を持っているので、原理的にはどの菌株でもアミノ酸生産菌となり得る。しかし、微生物ではアミノ酸の生合成経路は厳密に制御されていて、必要な量しかアミノ酸をつくらない。微生物によるアミノ酸の工業的生産を達成するためには、「必要以上にアミノ酸をつくらない」制御機構をはずして、その潜在能力を引き出すように微生物を育種・改良しなければならない。そこで代謝調節に関わる各種変異株が作出され、また様々なバイオテクノロジー技術が開発導入された。タンパク質を構成する20種類のアミノ酸は、現在ではすべて発酵法あるいは微生物酵素法で生産でき、調味料だけでなく、食品添加物、サプリメント、医薬品、飼料添加物、化成品、化粧品などに幅広く用いられている。このように、日本で生まれたアミノ酸発酵は長足の進歩を遂げ、世界のアミノ酸市場の過半を生産する技術に成長した。
発酵食品 発酵食品は有史以前から存在し、最古の発酵食品は8000年前のコーカサス地方のワインといわれているが、発酵乳の歴史も大変古い。主な発酵食品の種類を挙げると、清酒、ワイン、ビール、醸造酢、味醂、甘酒、醤油、味噌、納豆、発酵豆腐、パン、テンペ(インドネシア)、鰹節、塩辛、くさや、馴れ寿司、魚醤、塩蔵アンチョビ(ヨーロッパ)、シュールストレミング(スウェーデン)、キビヤック(イヌイット)、野菜の漬物(日本)、キムチ、ザワークラウト、発酵豆乳、発酵果汁、微生物発酵茶、発酵乳、フレッシュチーズ、熟成タイプのチーズ、発酵バター、発酵肉製品(サラミソーセージなど)がある。それぞれ関与する微生物の種類や保存性向上、特有の香味発生等に特徴があるが、ここでは発酵乳製品について述べる。
わが国における発酵乳製品の歴史 1900年に七塚原種畜牧場でチーズの製造試験が行われ、同年函館のトラピスト修道院で生産が開始された。乳業各社による企業的生産が始まるのは大正中期から昭和初期にかけてである。発酵乳については、明治時代末に“凝乳”と称して販売された記録があるが、ヨーグルトとしては広島合資ミルク会社(チチヤス㈱の前身)が1917年に初めて販売したといわれている。三島海雲が1919年に発売した加糖殺菌発酵乳(カルピス㈱)は、脱脂乳を原料とする日本独自の乳製品である。一方、腸管内で有用な働きをする乳酸菌に着目して代田稔は1930年に乳酸桿菌(ラクトバチルス・カゼイ)シロタ株を分離し、1935年に代田保護菌研究所(㈱ヤクルト本社の前身)から乳酸菌飲料ヤクルトが販売された。乳酸菌飲料も日本で開発され、世界各国に普及した食品であり、乳製品乳酸菌飲料は“発酵乳を基とした飲料”(発酵乳含量40%以上)としてコーデックス発酵乳規格に追加され、新たな国際規格(2010)として採択された。
乳酸菌利用範囲の拡大とスターター技術の進歩 乳酸菌は乳製品をはじめ各種発酵食品の製造だけでなく、サイレージや医薬品など多岐にわたる分野で利用されてきた。乳酸菌がつくる有用物質として、乳酸、ナイシン、血圧降下ペプチド、GABA、菌体外多糖(デキストラン、ケフィランなど)が利用されている。また、乳酸菌の産生する光学活性乳酸を原料とするポリ乳酸は1990年代に工業的に生産が開始され、21世紀に入ると再生可能なバイオマス資源を利用した生分解性プラスチックとして注目されている。
発酵食品の製造に用いる乳酸菌スターターの調製法には、フレッシュカルチャー法と濃縮スターター法の2通りがある。フレッシュカルチャー法は種菌からマザースターターを経て段階的にスケールアップし、最終製品に添加する伝統的な手法で、わが国でも従来から広く用いられてきた。これに対して濃縮スターター法は近年開発された方法で、使用する菌株を大規模に中和(定pH)培養し、遠心分離や膜処理で1010~1011/ml程度まで濃縮した菌液を液体窒素凍結あるいは凍結乾燥したもので、バルクスターターあるいは原料ミックスに直接接種できる。現在では専門メーカーから各種の濃縮スターターが市販されていて、乳酸菌の使用経験が少ない業界でも容易に利用でき、乳酸菌の用途拡大に寄与した。
食品保蔵における乳酸菌の働き 乳酸菌が生成する乳酸とそれに伴うpHの低下のほか、副生する少量の揮発性脂肪酸(酢酸、ギ酸)、過酸化水素、アセトアルデヒド、3‐ハイドロキシプロピオンアルデヒドなどは有害微生物(食中毒細菌、腐敗細菌)を抑制する効果をもつ。最近は“人々が長年にわたり食品として、あるいは食品とともに、何らの害作用もなしに食べてきた植物・動物あるいは微生物起源の抗菌性物質”(バイオプリザバティブ)を利用した食品保蔵技術が重視されている。乳酸菌とその発酵生産物は代表的なバイオプリザバティブである。最近特に注目されるのはラクトコックス・ラクチスが生成するナイシンであり、米国食品医薬品庁がGRAS(Generally Recognized As Safe)として認めている。ナイシンは34個のアミノ酸残基から成るペプチドでグラム陽性細菌全般に抗菌活性を示し、特にバチルスやクロストリジウム属の耐熱性芽胞に対する阻害作用は食品工業において有用と考えられる。わが国でも2009年に食品添加物(保存料、製造用剤:使用基準あり)として認可された。
プロバイオティクスとしての乳酸菌の機能 1989年にR・フラーは“腸内菌叢のバランスを改善することにより宿主に好ましい効果をもたらす生きた微生物”をプロバイオティクスと定義した。最近は“宿主の健康とその維持・増進に有益な効果を示す微生物とそれを含む食品”と拡大された定義も用いられる。代表的なプロバイオティクスとして、ラクトバチルス(L)・カゼイ、L・ラムノーサス、L・アシドフィルス、L・ガセリなどのほか、ビフィズス菌のいくつかの菌種に属する特定の菌株がよく知られているが、そのほかの乳酸菌・ビフィズス菌でも効果が検討されつつある。プロバイオティクスに期待される保健効果を表1にまとめて示した。紙幅に限りがあるので、個々の項目について現在蓄積されつつある科学的エビデンスの紹介は割愛するが、興味のある方は参考書④、⑤をご覧いただきたい。乳酸菌の保健効果に関しては、わが国で発見され、研究が深化した事例が多く、この面での国際的貢献は高く評価されるべきであろう。20世紀初頭にE・メチニコフが「長寿の研究-楽観論者のエッセイ」(1908)を著わし、ヨーグルト摂取による不老長寿説を唱えてから丁度100年後にラクトコックスに属する菌株でマウスの老化抑制効果が見出された。生活習慣病を予防し、私たちの健康寿命の延長に役立つプロバイオティクスについての研究・開発のさらなる発展が期待される。
表1 プロバイオティック乳酸菌に期待される保健効果
-----------------------------------------------------------------------------
整腸作用(腸内環境改善、便秘改善、下痢防止、栄養素の消化吸収改善)
感染防御作用
発がんリスク低減作用
免疫調節作用
アレルギー軽減・抑制作用
炎症性腸疾患改善作用
血圧降下作用
脂質代謝改善(血中コレステロール低減など)
ピロリ菌感染による胃炎の予防
乳糖不耐症状改善
-----------------------------------------------------------------------------

